ドクタケの出城が焼け落ちる爆音の中。
あの声が耳にこびり付いて離れない。
もがくあの人を押さえ付けて、迫り来る熱風からジリジリと退く。
前髪の焼け焦げる嫌な臭いの中、あの人は闇に落ちた。
もう…二度と戻って来れない闇に。
「…利吉さん?」
長屋の戸を背にした乱太郎が無邪気に笑いかけてくる。
しかし、以前はただ無邪気に見えた笑顔が様々な翳りを帯びている事を、利吉は知っている。
もう、以前のような子供ではなかった。
それは、年齢という意味だけでは無い。
「あぁ…もう、冬休みの季節なんですね。寒い筈だ」
乱太郎は、もう忍術学園を卒業していた。
今は、医者と忍者という奇妙な二足の草鞋を履いて生活している。
医者としての技術が確かな為、前者に重きを置くことになっているが、もう一つの大きな理由が、乱太郎が出てきた長屋にある。
正しくは、居る。
「乱太郎?どうした…」
長屋の中から、声が掛かる。
利吉の耳慣れた声。
乱太郎は、戸を僅かに開け、中に声を掛ける。
その言葉は利吉の耳にまでは届かなかったが、乱太郎は、再び戸を後ろ手に閉める。
「利吉さん、ちょっと…」
神妙な面持ちで、乱太郎は利吉に向き合った。
「利吉さん…」
乱太郎が話し出そうとするのを、利吉が遮る。
「…ほっとするな。そうやって、名前で呼ばれると」
「利吉さんは、利吉さんでしょう?」
「学園では、専ら『山田先生』だからネ」
利吉は、口の端だけを引き上げるように笑う。
利吉は、乱太郎達が卒業後、学園に教師として就任した。
先生と呼ばれることは、至極当たり前の事だ。
「私達にとって、『山田先生』は山田伝蔵だけです」
は…っ、と気付いた様に、乱太郎は口元を押さえた。
「そうだね。『私達にとって』……か」
「すみません。」
「謝る事じゃない。当然のことだ。山田伝蔵―父上が、君達にとって良き教師であった事は私にとっても…大きな誇りだヨ」
そう言って、利吉は遠い目をする。
そんな利吉に、乱太郎は恐る恐るといった感じに言葉を繋ぐ。
「だからこそ、利吉さんは…もう、ここには来ない方が……」
「それは、医師としての判断かい?」
「違うよ!利吉さん」
乱太郎は、昔の様に首を大きく振る。
「利吉さんの為…ううん、二人の為にも…」
「そんな事は無い!」
再び、乱太郎の言葉を遮る利吉。
そして、子供に言い含めるように語るのだ。
「あの人に会わない事が、私の為にならないなんて、あるはずが無いだろう?それに…」
あの時、利吉の想いは近しい人に隠しておくことなど、出来なかった。
利吉とて、究極の状況だったのだ。
その想いがある限り、今のあの人を放っておくことなんて、出来ない。
忍術学園の教師として、共に生活する事は出来ないが、忍びの任務で家を空ける事の多いきり丸一人に任せておくことなど、とても出来ない。
何より、利吉自身が耐えられなかった。
もし…医師として、強固に反対されたのなら。
それでも、
……会わないことなど、とても出来そうにない。
「あの人も、私を待っているんだから」
「…利吉さん」
乱太郎は、酷く苦しそうに笑う。
彼は、こうして笑うことで…辛いことを乗り越えて来たのかもしれない。
利吉にも分かっている。
いつか、時間が解決してくれる…そう儚い願いを抱いているのだ。
少なくとも、あの人は待っている。
私では…ない私を。
戸を開け、中に入ると…そこは昔と変わらない長屋風情。
相変わらず、必要最小限の家財道具しか無い部屋に、あの人―土井半助は横たわっていた。
利吉を見付けると、子供に戻ったような顔で微笑み、甘やかな声で呼ぶ。
「山田先生っ!」
両腕でいざるように近付いてこようとさえする。
「…土井先生」
そう利吉を呼ぶ愛しい人は、右足が膝上から下が…無かった。
乱太郎達、山田伝蔵と土井半助が、トラブルを日常として担任した元・一年は組が成長し、卒業を間近に控えた頃、長年煮え湯を飲まされて来たドクタケ忍者達は、一矢を報いんと、命がけの作戦を仕掛けて来た。
その形振り構わない策略に落ちた後輩忍たま下級生を、元・は組の良い子達、そして伝蔵、半助が見捨てられる筈もなく、罠と知りつつ強行突破を余儀なくされた。
繰り返される発破によって崩れ落ちる出城から、多くの人質と生徒達を逃がすのは、ベテラン教師を持ってしても、無理があった。
半助の中に、それまでのドクタケとの戦いを踏まえた甘えがあった。
しんがりを務めたのは、伝蔵と半助。
それは、いつものように助っ人として現れた利吉をもってしても、脱出は困難な状況で…。
利吉は託されたのだ。
崩れ落ちた瓦礫で身動きが出来なくなっていた二人。
伝蔵は、下半身が埋もれた状態で、利吉一人ではどうにも出来なかった。
伝蔵に庇われる形だった半助は、足を犠牲にすれば、抜け出す事が出来た。
半助の足を切り落としたのは、伝蔵だった。
そして…伝蔵は、利吉に半助を託したのだ。
半狂乱になる半助を連れ出したのは利吉だった。
「どうして!どうしてこんな、なんで…っ!」
あの時、意識を失うまで半助が上げ続けていた慟哭が、今でも耳から離れない。
九死に一生を得て、意識を取り戻した半助はある意味、正気では無かった。
記憶の中の何処にも、利吉はいなかった。
残酷にも、利吉という存在を伝蔵で塗りつぶしたのだ。
号泣する生徒達の中、新野は努めて冷静に分析した。
「土井先生の心が…山田先生の死を認められなかったのでしょう。」
利吉は、絶句した。
そして、嫌という程に、半助の伝蔵への…同僚を越えた気持ちを思い知らされたのだ。
―伝蔵が居なくては…生きていけないという事。
ただでさえ、父という心の屋台骨を失った…しかも、ある意味見捨てた直後のこと。
利吉は、抑えきれずに長年秘めていた半助への思慕の念を吐露し、新野に縋った。
僅かばかりにも積み上げて来た、それまでの全てを亡き者とされてしまうのは、余りに辛い。
それは、自分の存在全てが、自分の愛しく想う人から否定されてしまうのと同じ事だった。
何とか、して下さい!と。
しかし、新野は判断する。
心の問題は、どうすることも出来ないと。
そこまでして半助が守った自我を壊してしまうことにもなりかねない…と。
そのまま学園をリタイヤすることになった半助。
学園を卒業し、フリーの忍者になったきり丸が、面倒を見ることになった。
きり丸のことは分かる。
乱太郎のことも…。
分からないのは利吉のことだけ。
その上、利吉が姿を見せないと、半助は酷く不安定になった。
治りかけの傷を開き、その傷が何故あるのか…自分の作った心の防壁を破ってしまおうとするのだ。
それは、半助にとって死を意味する。
利吉の姿を見て、山田伝蔵は生きている…と、また心の歪みから目を反らす。
半助が、命の綱渡りをしているのを、利吉はすぐ近くで見詰める。
身体は触れ合う程に近いのに、心は遙か遠かった。
それでも…利吉は、半助から離れられない。
もし今度、伝蔵の死を認識し、それに耐えられたとする。
それでは…
利吉ごと全てを切り捨てられてしまうのでは?
そんな恐怖が付きまとう。
「山田先生…」
半助が、するりと利吉に擦り寄ってくる。
「…土井先生」
利吉がそう呼ぶと、半助は目を伏せ、首を振る。
「もう、私は…教師じゃないですよ。名前で…呼んで下さい。」
「…半助」
そう呼ぶと、自分からそう言った癖に、恥じらう半助を可愛らしいと思う。
消毒液の香りの残る部屋で、横たわる半助は、僅かにあった筋肉もすっかり落ちて華奢になってしまった。
するり…と、肩から寝間着を落とすと、尖ってしまった肩からの稜線が痛々しい。
それでいて、堪らなく利吉を煽った。
気が付くと、半助がじっ…と利吉の顔を見詰めていた。
その何処か曇った瞳に映る卑怯な自分が見ていられずに、利吉は半助を背後から抱く。
指先で、ぷくりとした感触の残る唇に触れ、軽く歯列をなぞってから、ゆっくりと下ろして行く。
次第に艶を帯びる半助の声。
「…山田先生」
利吉が、その呼び方を変えさせることは無い。
下の名前で呼ばれるのは、堪らなかった。
今は、利吉も教師。
山田先生…と称される立場だ。
屁理屈なのは分かっている。
それでも、今の半助の口から「伝蔵」という名前は聞きたくなかった。
軽く嫌がる顎を持ち上げ、首筋から、肩口へと唇を落としていく。
その一見、それらしくない箇所であっても、きつく吸い上げてやると、半助の息が上がる。
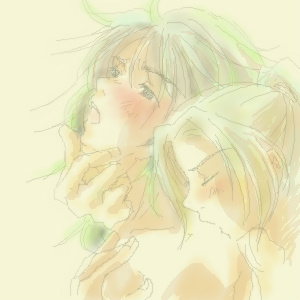
とても手放せないと思った。
一度手にしたものを、とても手放せない。
乱太郎の忠告は、痛いほどに分かっている。
でも…
あまりの不毛さに呆れられたとしても、理屈では無い。
酷く歪んだ逢瀬だが、二人にとっては…どうしても必要なのだ。
そうだと…思いたかった。
「どうして!どうしてこんな、なんで…っ!」
半助が半助であった時の最後の言葉。
利吉は思う。
それを聞きたいのは…私のほうです、と。
情事の余韻に浸る半助。
その表情は、残酷にも……うっすらと微笑んでいた。
■塗抹■―05.12.08