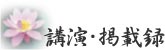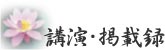「今を生きる」第145回 大分合同新聞 平成22年6月14日(月)朝刊 文化欄掲載
老病死を受けとめる(11)
95歳の男性、種々の病気を患って寝たきりになって入院してこられました。意識はしっかりしていて、亭主関白の傾向のあり、わがままなところがあるようです。奥さんは高齢ですが毎日病院へ来て夫に尽くす人でした。
この男性の食欲がおちて全身状態が少し悪くなり、本人が「こんな状態なら、死んだ方がいい」と家族に言うようになった。そんな時、奥さんが「前の病院で病気の悪いことはすでに聞いています。でも、本人には本当の病名や病状が悪いことは言わないでほしい。気を落とすから」と言ってきました。
日本の医療現場で、ガンを告知するようになって約20年が経過しています。しかし、「死を連想させる病名は言わないでほしい」という患者や家族はまだ多いのです。医師の一部も病名を言った後の対応が難しいためと、告知を受けた患者や家族の不安や悲嘆に対応する死生観を持たないために、言わないことが患者さんのためによいと考えているところもあります。
しかし、それは医師、患者共に死を受容する文化を持ってこなかったからだと思われます。日本人の多数が、老病死などの暗いものはできるだけ見ないようにして、明るい、楽しいことに目を向けようとしているためではないでしょうか。
病状の進んだガン患者から「もう治らないのではないでしょうか」と問われたある医師が、とっさに「そんな弱音をはいたらダメですよ、頑張りましょう」と言いました。患者は「ハア」と言って会話が途絶えてしまいました。入院後しばらくして良い人間関係ができたその患者さんが,その時のことを「『もうがんばれない、少し弱音を吐きたい、つらさを分かってほしい』と思っていたが、言い出せず、やるせない思いが残った」と教えてくれたといいます。
医師は老病死を受容する死生観を持ってなかったために、患者さんに寄り添う対話ができてなかったことに気づかされたのでした。 |