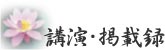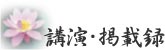「今を生きる」第237回 大分合同新聞 平成26年4月7日(月)朝刊 文化欄掲載
医療文化と仏教文化(64)
老病死をどう受容するかは臨床の現場でしばしば出合う課題です。いとこが腎臓がんで亡くなる前、「種々の治療で効果がなければ、痛みを取る緩和ケアに移った対応をした方がいいのではないか」と告げたとき、彼は「明るい方向が見ないということはいたたまれないんだ」と発言したことが思い出されます。
病状の進んだがんの患者さんと関わるとき、身体的な疼みはかなり対応できるのですが、患者さんとの対話が難しいのです。症状の進んだ状態で種々の不快を訴えて「良くなるじゃろか」と質問してきます。その患者さんは病気や症状が良くなることしか関心を示さないのです。
自分や自分の周囲に幸せのためのプラス条件を集めて幸せになろうと考えている多くの人には、老病死はマイナス条件でしかないのです。もう治癒できないという病状を告げられ、種々の痛みの緩和治療しかできないと言われて、その後をどう過ごすかという問題です。仏教では人生を味わい直すチャンスが残こされていると教えているのではないでしょうか。
自分自身が胃がんになり、進行がんで根本治療ができないと知った某医師が「死に往く者の道しるべを失った日本の文化に驚いた」と書かれていました。それがきっかけで、東北大学に臨床宗教師を育てるコースが2年前から始まりました。
医療は身体的な苦痛にはかなり対応できるようになっているのです。しかし、心や気持ちの領域で「明るい方向が見えないといたたまれない」という課題に医学・医療は対応できているでしょうか。それは個人の内的な問題で医療が関わるべきでない、という姿勢で避けたり、逃げてきたというしかありません。学んできた医学では対応できないからです。
病人を相手の全人的な対応より、病気だけを相手の局所的医療の方が医師にとっての負担は少ないと思われます。専門性を高めて、その領域の専門医となる方が、人間全体を相手にする領域の医療よりは専門的知識が発揮できるからです。人間全体に対応しようとすると、未知なる部分が多く、非常に複雑な心の領域もあり、対応は困難になります。 |