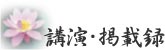 |
講題「医師という『師』の名称の付く意味」 佐藤第二病院 田畑正久 第28回日本臨床麻酔学会 京都国際会議。平成20年11月21日 ■要旨: 医療と仏教は生老病死の四苦を共通の課題とする。医療は元気でイキイキした「生」を目指している、そのために「老病死」の現実を受容する視点に欠けていた。治療の概念からいうと老い、病み、そして死ぬことは敗北、不幸の完成である。四苦に対応するに、最終ゴールは不幸の完成でよいのか。「老」とは「老成」、「長老」の言葉が示すように本来、成熟することへの敬称である。成熟は仏教の智慧と深い関係があり、仏教で成熟した人格者は「人間に生まれて良かった。生きてきて良かった。死んでいくこともお任せです」と鷹揚に生きていかれる。医師の「師」とは人生全体を見渡して、生きていることの喜びと老病死を受容して四苦を超える道への素養をもつ人格者であることが期待されている。 1.はじめに 私は外科医として仕事をしてきました。私は九州大学の卒業で、九大には先輩方が診療所、健康相談、無医地区巡回診療等のボランティア活動をする仏教青年会(仏青)があります。その加勢をする学生は部屋代がただで生活ができる寮があり、私は仏教には関心がなかったのですが、部屋代がただの方にひかれて仏青の寮に入りました。それが縁で仏教の学びをさせていただくようになり、卒後は外科医として勉強してきました。今日は仏教の学びを通して気づいたことをお話させていただきます。 2.医療と仏教の協力関係 日本では「医療と仏教の協力関係」がうまくできていません。「生きているうちは医療、亡くなってからは仏教」というイメージが強いのです。 医療の課題は人間が生まれ、老い、病気で、死んでいく、この生老病死の課題に医学は取り組んでいます。仏教もこの生老病死の課題に取り組んでいます。同じことを課題としながら、協力関係ができてないことは日本の文化においては不幸なことだと思っています。 埼玉医科大学の哲学教授をされていた秋月龍珉師(臨済宗、師家)が医学部の学生に、「皆さんは将来医療という仕事に携わる、医療は人間の生老病死の課題に取り組んでいるのです。同じ課題に取り組んで来たのが仏教の2600年の歴史です。医療の仕事をする者は是非とも仏教的素養というものを持ってほしい」と語りかけてきたということを本で読んだ時に、私は外科の仕事をしながら仏教の学びをするということが、同じ課題なのだと気づいて勇気づけられました。 医療に従事してきて、仏教の学びから気づかされることは、医学教育だけでは人間の生老病死の課題に十分に対応できないということです。日本が西欧から医学を学ぶ時に医療知識・技術を学ぶことには一所懸命だったけど、その精神性を学ぶことはほとんどしてこなかったのです。宗教抜きの医学を取り入れてきたのです。緩和ケアに携わっている知人が言われるには、日本の医学教育はもともと軍医養成、元気な国民(兵隊)を育てる、軍医養成から始まったという。だから、元気にするところまでは一所懸命するが、元気でなくなってから、老病死につかまってからは、どうしたらよいかということは教えてこなかった。いや、学んでこなかったと。 私たちが学んだ医学は症状を聞いて、診断をつけて、治療して、少しリハビリするくらいまであるけど、その後はほとんど教科書にも記載がない。しかし、外科医をしていますと、治療してよくなっていく患者は喜んで「よかったですね」と送りだせるのですが、よくならなかった、再発をした、そういう人たちに対して私たちはどう対応したらよいのかということは教科書には出ていない。そういう患者は医学の世界からは見捨てられたというか、あきらめるしかないと、そういう対応で私自身も大学教育の中でそういうような場面を見ていました。しかし、よい人間関係ができた後、そういうことでよいのだろうか、何かできることはないのだろうか。私も卒後35年が過ぎ、長年、医療の仕事をしてみると、よくなる病気はよくなる。よくならん病気はよくならないと気づいてきます。そういうよくならない人に対しても私たちは何か対応する心があってもいいのではないかという思いがいたします。 麻酔科医は、手術の前後の管理という役割においては、人間的な接点というのがわりに少ないかもしれませんけども、緩和ケアとかペインクリニック等で、痛み、苦痛に悩んでいる患者との関係の中で、よい人間関係ができて、そしてそういう人たちにどう対応したらよいのかということは、長年医師という仕事をして来れば必ずそういう問題に出くわす。そのときに、我々が受けてきた医学教育だけで十分だろうかという思いを持つようになるでしょう。 3.「師」の意味するもの 私たちは国家試験を受けて医師という資格を受けております。でもこの「師」ということの意味は、辞書では、昔中国で軍隊を率いる人、軍隊を率いて指揮する人を「師」と呼んでいたことから、人々を導く人を「師」と呼ぶようになったと。こういうふうに教師、医師、看護師という名前、「師」という名前がつくということは、多くの人たちを導く、人間としての指導をする「師」という意味が本来はあるのです。医師という名称を私たちは職業としていただいておりますが、人間としての道に、十分な「師」たりえているだろうかと。 昨日のニュースで総理大臣が「医師というのは社会的常識を欠く人が多い」と失言して、謝罪をしておりましたけども、私は田舎の病院長を10年しておりましたから、麻生さんが言っていることは本当ではないかと思う場面が何回もありました、そうでない先生方も多いのですけども、多くの国民にはそう映っているかもしれません。 私は浄土真宗の学びをしてきましたが。浄土真宗で「門徒もの知らず」という言葉があります。「門徒もの知らず」というのは浄土真宗の信心をいただく者は「常識を知らない」とこう言われるのです。信心のある門徒は、日の善し悪しを言わない、方角を気にしない。占い、迷信に執われないので、「常識がない」という言われ方をされるのです。社会的常識が正しい基準ではありませんけども。 4.能力について そこで人間としての「師」とはどういうふうに考えていったらよいのだろうか。先生方は麻酔科医としての資格というか認定を受けられていることだと思います、専門医としての認定とは能力でいうとabilityに対してでしょう。能力については英語ではabilityとcapacityという2つの言葉があります。abilityもcapacityも能力ですが、調べてみますとこのabilityとはいろんな知識をもって仕事をてきぱきと対応する、患者の刻々の変化に対して適切な処置をする、そういう処置をする、対応する能力をabilityといいます。これは試験でテストすることができます。 capacityというのは人間関係調整能力と言われるようなものです。その人の人格性といいますか、その人と居るとなんとなく温かい、その人と居ると何んとなくくつろぐ、この人の前ではなんでも言えるという、そういう人間性、人格性というようなものがcapacityという形で言われている能力なのです。このcapacityという能力は医師の国家試験や専門医の認定、その中でテストを受けているかというと受けてないのです。医療という仕事は人を援助する仕事です。対人援助の仕事、教育、医療、福祉、人を相手の仕事というのは、capacityというのは、なくてはならない能力なのです。abilityはある基準以上なければならないけれど。 私が住んでいる宇佐市は、市長に大学の先輩の医師がなっています。この先生が開業医の開業祝いでよく言われることは、開業医がはやる要領があるといって、「一に在宅、二に愛嬌、三、四がなくて、五に技術」とこういいます。それぐらい在宅と愛嬌という人間関係の温かさが求められているのです。capacityの領域が実践の医療の場では人々から求められているということです。 私たちは最新の医学の進歩を学会等で学び、医療の現場で実践するということが非常に大事です。でもそういう最新の知識だけでは医療の仕事をする場合に不充分で、患者との関係、職員との関係、ここのところにcapacityということが非常に私は大事になってくる。そしてよい関係・環境が出来ると自分の力量を十二分に発揮できるようになるのです。 医療の現場が単にビジネスの関係だけだと、医療の仕事は老病死に関わることで、治癒する場合はよいのですが、最終的には死、敗北という形で仕事が終わるという場合には、医療関係者当に「燃え尽き症候群」といわれるようなことがおこるということを皆さん方も感じていると思います。 私の知人で別府市で約400床ぐらいの病院の副院長をしている外科医が教えてくれたことですが、「ある農協の組合長さんが大腸がんで入院してきた。十分説明して手術をした。それは無事に乗り越えた。2年後に肺転移をきたした。それで肺転移の手術もした。その後、経過をみていたら、今度は肝臓のほうに転移が見つかった。それで肝臓の方もまた手術をした。これまでの経過についても、病状についても十分に説明をして、ガンという説明もしていたのです。だけども3回目の肝転移のときに、入院中に骨への転移が見つかり、化学療法をし始めてだんだん弱っていって、そして亡くなる3日前にその患者さんから、『だましたな』とこう言われて気まずい雰囲気のまま最期亡くなっていかれた」と。 患者にとっても、一所懸命治療してきた医師にとっても、最後に「だましたな」という関係で終わっていくということは、本当に報われないといいますか、そこに病気を縁として病気と戦ってきた仲間、心が通じる、協力するという関係ができる状況というものが私はあってほしいな、いやそういう関係を作っていかないと医師としての技量、力量を十分に発揮できないと思われました。 5.人間性、人格性 ビジネスの関係だけでよいという人もいますけども、患者との関係でよい信頼関係ができることが、結果として症状の改善に結びつく、病気もよくなっていく展開になる要素があるわけです。そういう人間関係調整能力といわれるようなcapacityというような領域のことは、知識教育の中ではなかなか伝えられないというか、学べない、そこに人格と人格との接点がなければ、こういうものは伝わらないと思っております。 普通、私たちは学問的な、学校の成績のよい人、能力のある人は理性的にも知性的にも十分に自分を律することができると考えておりますけど、ある僧侶が「学問的な能力ということと、お金に関する倫理性とか異性に対する倫理性というのは比例しない」と言っています。必ずしも学問的な能力が人間性、人格生と比例するとはかぎらない。私は、比例すると思っていたのですけども、そうじゃないのだと言われてみて、改めて「ああそうだな」というような感じがしています。 医学を学んできた者がどういう点で、人格性を磨くことへの接点が少なくなってきたのかというと、私たちが習ってきた医学というのは唯物論的な対象論理の科学的合理思考に関係するのではないかと思われます。形で表せるもの、色で表せるもの、数字で表せるものを確かなものとして、必ず実証できることをevidenceという形で尊重して積み重ねてきた医学教育に依るからです。 6.対象化、対象論理 そういう理性知性だけで私たちは人間全体を十分に把握できるだろうかということがあります。人間というのは常に変化していますから、それを情報化して把握をしないといけない。皆さん方が手術中にはいろんなモニターを使いながら患者の情報を経過とともに見ながら、その状況、状況に応じた対応をしていくということが医師には求められています。そういう意味では瞬時に情報が変わっていく。その情報を情報化した時にはこれは固定化したわけです。この固定化したものはその時の情報であって、その5分後、10分後にはまた新しい情報がなければ、患者の把握はできない。全体を把握するためにはいろんな情報を集めて患者の状況把握をしないとなりません。 これで思い出すことは、東大元教授の養老孟司先生が、おもしろいこと言っています。解剖学の研究をしていたころは内科とか外科の臨床の先生から、「スルメを見てイカがわかるか」という皮肉を言われていたそうです。「スルメを見てイカがわかるか」と。スルメというのは、イカを干して食用にした死んだ状態をスルメといいます。「死んだ人間を見て、生きている人間がわかるか」とこういう皮肉を言われていたそうです。先生が最近人間ドックに行ったのだそうです。そしたら、担当の医師が血液の検査、胸の写真、CT等の結果をみて、ほとんど診察をせずに、どこが悪いとか、よいとか言ったと。それで今こそ、「スルメを見てイカがわかるか」という言葉を返してあげたい、と書かれていました。 私たちは生きている人間、刻々と変化する人間の全体を把握しようとすると、どうしても情報をたくさん集めないといけない。今はいろんな情報がモニターされています。患者の情報を集めて私たちは患者の全体像をいかに正確に把握するかということで、苦労し、工夫しているわけですが、私たちが学んできた医学は、そういう実証できるとか、科学的思考の下で捉えようとしています、この科学的思考では全体を把握することに欠点があるのだということを私たちは注意しないといけません。 母の涙ということを科学的分析的に調べますと、母の涙は秋の物悲しい季節に落ちることが多い。涙の分析はH20が何%で、NaClが何%で、ボリュームは平均何mlだと。で、比重がなんぼで、涙腺の涙の分泌様式はなになにだ、等と、分析して、その分析した結果を再統合して母の涙ということの全体像が把握できるかというと、私たちの学んできた科学的合理主義というのは感情、感性、数字に表せない、形に表せない、そういうようなものが全部抜け落ちていってしまうのです。 医学教育の中でいつのまにかそういう見えないものを無視して、見えるものだけ、形に表せるものだけを見て、全体を見たつもりになってきた。これで人間理解が十分になされているだろうかと考えないといけない。それは仏教の智慧が教えてくれていることなのです。 7.分段生死 仏教の学びから見えてきた、医学教育を受けてきた者の陥り易い欠点を、少し紹介をします。まず、その人間の生老病死に関して、医師の治療、cureという概念は、元気で若々しく生き生きとした「生」だけが本来のあるべき姿であって、不老不死をめざせといって、いつのまにか老病死はあってはならないものだ、老病死を先送りし、元気さをいかに保つか、ということを一所懸命やっているのです。 そして「生きている」ということと「死んでいる」ことをはっきりと分断するわけです、分断生死と。人間が生まれて生きて老いて病気で死んでいくというこの自然の経過をいつのまにか「生きている」ということと「死んでいる」ということは別々のことなのだ、と考えるようになってきた。私たちも救急外来で患者が運ばれてきますと、その人は生きているか、死んでいるかの区別をします。そして、明らかに死んでいる人に対してはもう何もしない。それは検死ということになります。生きている可能性のある人には蘇生術をして治療をするという展開になっていくのです。そこでは「生きている」ということは「死んでない」ということなのだ。「死んでいる」ということは「生きてない」ということなのだと、「生きている」ということと「死んでいる」ことをはっきり区別する。その延長線上で、老病死は私たちの元気で活き活き生きる「生」を邪魔するものだ、妨げるものだとこういうふうになっていくわけです。老病死をできるだけ無いようにしていこうとして元気な「生」を維持していこうとこうする。しかし、宗教学者たちは老病死を拒否してしまうと、生きることの輝き、生きることの意味がなくなっていくと言われています。 ここが私たち医学教育を受けてきた者にはなかなか受け取れない。できるだけ老病死をなくしていって、「生きる」ということだけでよいじゃないか、と言いたいわけです。「死」というものを見つめない「生」というものは、本当に味気ないものになっていくのです。ここが現代人には理解できないところなのです。分断をするということに大きな一つの問題があります。 加賀乙彦さんという精神科医師(作家)が死刑囚と無期懲役の人たちの心理を研究しています。東京に死刑囚を集めた所があります。そこで50人の面接をしていったそうです。その棟はすごくにぎやかだそうです。歌を歌ったり、お経をあげたり、隣同士で将棋を指したり、もう騒然としているのだそうです。そこで50人の面接をした。たまたま朝、7時くらいに行ったら、あんなににぎやかだった所がしーんとしていると。どうしたことかと看守の人に聞いてみたら、日本では死刑執行の宣告は朝の7時から7時半の間に伝えられるのだそうです。だから今日は私の番かもしれないと、皆しーんとして、じっとしているのだそうです。そして7時半を過ぎたとたんに、うわーっとにぎやかになるのだと。それが毎日繰り返されるそうです。うわーっとなるというのはある意味では躁鬱病の躁に近いことかなと私は思うのです。 一方、無期懲役の人はどうだろうかと言うと、千葉にある施設を訪ねて無期懲役の人たちを百人ずっと面接したそうです。そこは死刑囚の人たちとはうって変わって、しーんとして静かにおとなしい。しかし、それは生きているといっても、生ける屍のごとく、まったく気力のない集団になっているというのです。たまたまソフトボールの試合があったので、見ていたら、一人の人がホームランを打った。だけど誰も拍手をしない。そしてそのホームランを打った人が時間つぶしをするかのごとく塁を回って帰ってきた。本当にふぬけみたいだったと。これを加賀さんは「刑務所ぼけ」とネーミングしています。 死刑囚として面接をした人が裁判で無期懲役に減刑になった、その人が千葉に移ってきた。にぎやかだった人が、一週間もしない内に皆と同じようにボーっとなっていったと。加賀さんはどういう考察をされているかといいますと、死刑囚の人たちには残っている時間は1日しかない。そのために、その1日をいかに使うかと凝縮された1日を生きる。無期懲役の人たちは、死ぬまで大丈夫だという。これは死ということに対峙していないので、死に対して切実性がない、死を身近に見てないがために、生きるということのactivityがおちてしまっているのだというのです。 私はよく生涯教育の中で、日本は医療・福祉は外国に比べればかなり充実しています。そういう意味では刑務所の外か、内かの違いがあっても、みんな無期懲役かもしれませんねとこういう話をするのです。常に死に裏打ちされている「生」というものがあって始めて生きるということが輝くのです、このように仏教は教えてくれているのです。 8.縁起の法 これは仏教の「縁起の法」といいまして、私たちはガンジス川の砂の数ほどの因や縁が仮に和合して「私」という現象としてあるのだと教えられるのです。現象としてあるということはしっかりした「我」はないのだ、「無我」なのだとこういうのです。縁しだいでは次々に変化をするという状態を無我とこういうのです。一刹那とは、今の時間になおすと75分の1秒です。75分の1秒毎に生滅を繰り返しているという。代謝ということを考えれば、決して矛盾はしてないと思います。 私たちはその老病死の死というものにどう対応するか、死の不安というものがあったときに、その対応がなかなかできないわけです。死を超えるというひとつの仏教的な視点はこういうことです。「昨日の夜、昨日の私は死んでいるのです。今日という初体験の一日が今日の朝始まったのです。そして、今日の夜、今日の私は死んでいくのです。そして、明日の朝、新しい私が誕生するのです。」ということは、私たちは人生の長さだけ毎日死ぬ練習をしてきたのですよということです。昨日の夜、昨日の私は死に、今日の朝今日の私が誕生し、今日の夜、今日の私は死んでいくのです。 そこで昨日の夜、眠る瞬間がわかったかと言いますと、眠る瞬間は人にはわからないのです。そうすると、ギリシアの哲学者が「生きているうちには絶対死なない」と。「死んだら死なんて考えない」とこう言っています。ということは、今、生きている、生かされていることを精一杯生き切っていけばよいのだという世界に導かれていくと言うことです。 「死の不安」を訴える患者がいます。仏教の学びから言うとこれは「取り越し苦労」なのです。この「取り越し苦労」に私たちはどう対応していくか。私たちが学んだ医学ではどうするように教えてくれているでしょうか?。 私の恩師の同僚が脳梗塞になった、症状が軽くて麻痺もなく退院できた。その人が今度脳梗塞になったら死ぬんじゃなかろうかと不安に襲われて、家に帰っても非常に不安で、奥さんに「夜脳梗塞になってもすぐわかるように隣におっとってくれ」と言った。そしたら奥さんが、「そんな子どもみたいなこと言いなさんなよ」と、つっけんどんに言われたものだからパニック障害になって、また入院した。 9.老病死への対応、受容 医学を学んできた者が死の不安に対して対応できるだろうか。一時しのぎはできますよ。抗不安薬と睡眠導入薬を処方して、その夜はなんとか越せる。だけど、次の日、朝起きて、死の不安がまた出てきたときに、そのことに対して私たちは対応できるだろうか。今までの医学教育だけでは対応できないのです。 老病死をどう受け止めていくかということに対して、これまでの医学教育の中からは対応は難しい、そういう訴えをする患者に対して、医師として、いわゆる「師」として、自分が決して「師」という資格があるとは思えません。その資格がないのだという謙虚さをもって対応するということは非常に大事なのです。俺は十分にやっているのだとこうなっていくと、そういう対応ができる人との協力関係ができないわけです。そこに自分としてcapacityという老病死の受容ということに対して、十分に対応できるだろうか。いや、できないとするならば、できる人との協力関係を是非とも作っていくことが求められるわけです。 私たちは「思い」と「現実」に差があることが苦しみになります。「思いどおりにならない」ということを中国で漢字の「苦」と訳したのです。思い通りにならない私たちの痛みとか病気を健康な状態にすることでその人の現実を思いの方にもっていくとことで、その差が小さくなる。これが医療という仕事で苦を少なくすることです。 臨床の現場で患者の苦しみ悩みを、病気を健康な状態に戻す、痛みのある状態を痛みのない状態にするということでその人の思いを実現して、苦悩を少なくしていこうとするわけです。でもこれはよくなる病気の場合だけなのです。よくならない病気、もう回復不可能な、リハビリしても元にもどらない障害、そういう現実になったときに健康な状態に戻してくれといわれた、として私たちはその差を埋めることができない。どうするか。 私たちの苦しみ、悩みというものをどう解決するかという方法を仏教はどう教えているかということを紹介します。仏教の信心、悟りというのは苦しみをとることを目的にしているわけではないが、仏教的な世界が本当にうなずけてくると、信心・悟りの世界においてこの現実を受け取るという、老病死を受容するという事実が展開するのです。 キリスト教では星野冨弘さんを紹介します。この方は中学校の体操の先生をしていて、授業中、誤って脊髄損傷となった。首から下が麻痺、そして今、口に筆をくわえて、いろんな植物の絵を描いて、そこに詩を書いております。その中の一つに「いのちが一番大切だと思っていた頃、生きるのが苦しかった。いのちよりも大切なものがあると知った日に、生きているのがうれしかった」があります。どういうことかと言ったら、健康が大事ですよ、障害がないということが大事ですよと思っていたときには、自分は回復不可能な障害を持ってこの差を縮めることができないから生きるのが苦しかった。しかし、その次に、「いのちよりも大切なものがあると知った日に、生きているのがうれしかった」とこういう表現になっているのです。いのちよりも大切なものがあるという宗教的な世界との接点が持ちえた時、生きているという現実がうれしかったと、こういう展開をされています。老病死という現実を受けとめて、生きていく勇気を持つことができたという感動の表現です。私たちは医療、医学教育だけでは、その受けとめる、という幅の広さ、奥の深さがなかなかもてないわけです。 そういう患者から相談を受けた場合、患者に対して私たちは老病死の現実を受け止めて生きていくという勇気をどうこの人に持っていただくことができるだろうか。このことは私たちが学んできた医学知識だけでは、どうもこれは間に合わない。そこに、星野さんの「いのちより大切なものがあると知った日に、生きているのがうれしかった」という、そういう宗教的な世界のことを私たちも少しは学び、またそういうことは医師ができないとするならば、そういう関係者とも協力を求めて、そういう人たちに「人間に生まれてよかった、生きてきてよかった」という人生を生き切っていただくという、こういう取り組みができると、私たち医師も患者も社会も本当に豊かということを実感できるのではと思います。 10.不幸の完成 今はそういうことが見向きもされない社会状況の中ではどうなっているかといいますと、多くの人たちは、みんな幸せ(本当の漢字は「仕合せ」です)になりたいと思っている。どうしたら幸せになれるだろうかというと、幸せのためのプラス条件を増やし、マイナス条件を減らせば、きっと幸せになれると思って、多くの人は、いや私たちも皆そのための努力をしています。しかし、幸せのためのプラス条件とマイナス条件という世間的なものさしだけを持っていたら、健康はプラス、病気はマイナス、役に立つ人間はプラス、役に立たない人間はマイナス、迷惑をかけることはマイナス、迷惑をかけないことはプラスだというものさしを持っている多くの高齢者の人たちが老病死につかまった現場で、「私なんか役にたたん、みんなに迷惑をかける」と私の患者で睡眠導入薬を飲んで自殺未遂を図った患者がいました。 そういう患者に対して、老病死に対して私たちはどう対応していったらよいのだろうかと考える時、このプラス価値を上げてマイナス価値を下げていけば必ず幸せになれるのだという私たちの生きる方向性というものは皆、老病死につかまったときに、老いることはマイナス、病もマイナス、死ぬこともマイナスというならば、まさにマイナスが集まって死んでいくということは不幸の完成で人生を終わっていくわけです。 日本国民1億2千万人が最後は不幸の完成で人生を終わるのですよ。「日本はすばらしい国ですね」と誰も言わないわけです。しかし、現実はこの老病死の受容ということができないとするならば、まさに最後には愚痴をいいながら、老病死で不幸の完成で人生を終わっていくという社会になろうとしているのが現実ではないでしょうか。 「人間に生まれてよかった、生きてきてよかった、死んでいくことにも何んの不安もない」というような文化を共有できるということが私は大事ではないだろうかと思います。「そういう問題はありません」と平然として居れる人たちは、それはそれでよいのですが、老病死という現実にぶつかったときに、それを受容できない社会・文化状況になっている現実。私たちは医療の中で人間の生老病死の四苦に対応しながら、そのことに十分に対応できているだろうか。そういう訴えをしたときに患者にそんなこと考えなさんな、もうちょっと明るいことを考えなさいよと言って単に思考をそらすというか、ごまかすというか、そういう形でだけで十分に対応できるだろうか。 医師という仕事が人間の生老病死の四苦という課題に取り組んでいるのです。だから私たちは元気にする、治療するという一面では一所懸命最新の医学で実施していかなければならない。それと同時に老病死につかまった時においても十分にその人たちが「人間に生まれてよかった、生きてきたよかった、死んでいくことも何の心配もない」ということを、そういう世界を共有して、本当に生ききっていくというか、完全燃焼していくという文化を共有できるというか、そういうことに私たちも少しお手伝いができるということにおいて「師」と言われるに相応しいと言えるのではないでしょうか。私は生老病死の四苦を超える仏教の教えの学びを通してそういう世界を共有できるのではないかと思うのです。 残念ながら日本の戦後、我々が受けた教育には宗教性はほとんどなく、私たちは理性知性を一番しっかりしたものと考え、それで科学的思考というもの、これしかないというぐらいに教育をされてきたように思われます。しかし、それだけでは生きている人間を把握するには足りないのです。それはどうしてかといいますと、物事を私たちは向こう側に見るという、対象化という見方(対象論理)は自分を見るという視点が抜け落ちているのです。自分を抜きにしては全体の把握にならないのです。 11.内観で日本の文化に貢献 私たちは医学とかそういう科学的な思考の中では自分のことは私的なことだからそんなこと言わなくてもよいのだという傾向にありますけども、自分はいつも抜け落ちるという思考は、半分欠けているのだと仏教は言うのです。自分というものを見つめる目がなければ(考慮に入れないならば)全体の把握にならないのです。仏教は日本の文化になにを貢献したかと、これ内観というのです。自分で自分を見つめるのではなく、仏の智慧の光で照らされて自分の姿を知る(内観)ということが大事なのです。 自分のことは自分でわかっている、と思いたいわけですけども、もし自分のことは自分でわかっているというならば私が人間に生まれた意味をどういうふうに理解しているか、生きるということの意味を自分はわかっているか、死んでいくということの意味がちゃんとわかっているかと、このことが全部わかっていたら自分は自分のことが一番よくわかってるといえるかもしれません。 人間に生まれた意味をどういうふうに………、最近、意味というよりは物語、narrative based medicine(NBM)ということも言われるようになっています。この物語に基づいた医療、私たちが人間に生まれたという物語をどういうふうに理解しているか。生きていくということの意味をどういうふうに考えているか。死んでいくということの物語をどういうふうに理解しているか。このことまでを含めて私たちが自分のことは自分がよくわかっていると言える場合は、それはまさにそのとおりだと思います。しかし、私たちが受けてきた教育の科学的合理主義では人間に生まれた意味ということもわかりません。生きるということの意味もなかなかわかりません。死んでいくことの意味もなかなかわかりません。 これは私たちの大事な問題が抜け落ちているのです。一番大事な問題、生きるということの意味をどういうふうに考えているか。私たちは利用できるものはなんでも利用して、自分の欲を満たすためでよいじゃないかと、そんな思いを一般の人たちはもっております。しかし、自分の欲を満たすために私の周囲を利用するという関係は……………、行きつく所は、最後は「だましたな」という関係です。私たちはそういう人間関係をつくっていくと、これは非常に人間性を疎外していくことなのです、自分・他人ともに人間性が疎外されていくといいます。それは豊な人生ということには結びつかないと思われます。 仏教の智慧というものを最後になりますけども紹介します。世間的な知恵は「物事の表面的な価値を計算する見方」だといいます。役に立つ、役にたたない、迷惑をかける、迷惑をかけない。これは1万円の価値があるというふうに表面的な価値を計算するのは、世間的な知恵なのです。 仏教の智慧は「その物の背後にある意味を感得する見方」といいます。背後にある意味というのは、日本語の文化でいうならば、「ありがたい」とか、「もったいない」とか、「かたじけない」とかで表現されるものです。そのものの背後にあるもの、たとえば、私たちが食事をするときに「いただきます」というのは、その食卓にあがった動物・植物の多くの命、用意をしてくれた人の心をいただくという、ものの背後にあるものを感得するということが仏教の智慧です。 智慧では表面的には見えないが、背後に宿されている意味が見えてくる、そういう世界が見えてくると、仏教のある先輩は「年をとるというのは楽しいことですね、今まで見えなかった世界が見えるようになるんですよ」とこう言っています。仏教の智慧を学ぶことが人間としての成熟ということに結びつくと思います。 成熟ということに結びつくとどうなるかというと、京都大学の学長をされていた平沢 興先生が、「愚かさとは深い知性と謙虚さである」といわれています。自分の愚かさ、仏法の智慧に対して自分の愚かさがわかってくる、分かってくるのは、深い知性においてなのだと。そして深い知性において自分の愚かさが気づかされると必ず謙虚になる。 私たちは人間の生老病死の四苦に対応しながら、老病死の受容ということについて、ほとんど素養がない。そのことに対して謙虚になって、そのことのできる文化を学ぶ、いや、出来る人と協力をする。こういうことが今医療の世界で求められている。特に緩和ケアの領域では、私たちの学んできた、医学だけで老病死で回復不可能になってきた人に対して、十分に対応ができるだろうか。医師にそういうことができる医師になってほしいという願いはあるけども、そこまで期待したら、まさにスーパーマンです。できないなら、できないなりに、できる人との協力関係を作る。謙虚さをもって、チームを作って、そういう人と協力することが現代社会からの要請として求められているのではないでしょうか。 人間の老病死、自分自身の老病死をどう受け取って、どう生ききっていくか、ということが私は人間としての「師」といわれる人たちに求められているcapacityの中に含まれる人間性、人格性ではないか、と思います。 三木清という「人生論ノート」の著者の哲学者は、幸福についての項目に「幸福とは人格である」と書いています。私たちは幸福というのは人格と関係ないなと思っていたけど、この三木清は、仏教の智慧を身につけた人格の人が本当の幸福だと書いています。私たちは「幸せ」とか「幸福」とかいうことが単に物質的な豊かさだけで十分ではないのだということを謙虚に学び、本当にそういう人格性を学び、身に着けていくということが、私たち医師にも求められている時代性ではないでしょうか。医師という資格はそういう人格性がそなわっているということに対しての「医師」という名称ではないだろうか。 医師という職業はabilityだけではない、capacityというこの両方の能力というものを身につけいくということが本当に求められている仕事ではないかと思います。いやそのことが分かると、患者さんと接するということが、日々の歩みが、決して疲れたとか、燃え尽きただけでなく、本当に学び、成熟の縁となる出会いの場として喜べる職場ではないか、ということを思うことです。 会場からの感想に対しての応答; 私は前任地の今の国東市民病院に赴任するときに、私の郷里からちょっと遠く、国立病院から町立病院となんとなく都落ちするような感じはないか、自分自身のプライドが傷つけられるのではないか、とか。そこに赴任したらゆくゆく院長になれるのだろうか、とか煩悩まみれに考えていたら、仏教の先生から手紙がきたのです。どういう手紙かといいますと、手紙の一部に「あなたがしかるべき場所にいって、しかるべき役を演ずるということは今までお育ていただいたことに対する報恩行ですよ」とこう書かれていたのです。恩に報いる行だとこう言うわけです。 これは仏教ではなくても、大学からどういう学びをして、大学にどういうお返しをしたか。社会からどういう学びをして社会にどういうお返しをしたかといったときに、私自身は取ろう、取ろうとしていた。仏教で言うならば「餓鬼」というのです。もう40歳でしたけども、私の根性は本当に人間になれてなかった、餓鬼だったんだなと、本当に恥ずかしいという思いがしました。 やはりそこに自分では、自分は常識人だ、間違いない、と思っていたけども、仏法の先生を通して、あなたは本当に「人間になれていますか」とこういわれたときには、本当に恥ずかしいと、こういう思いをさせていただいたことがあります。そういう人との出会い、教えとの出会いというものが私は本当に大事ではないかと思っております。 |
|
(C)Copyright 1999-2017 Tannisho ni kiku kai. All right reserved. |