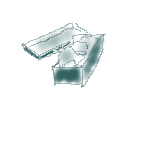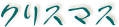
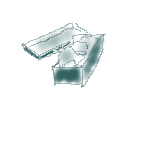
父はお祭り好きだった。夏は盆踊りや競馬場の花火大会、冬は氷川神社の十日町や調神社の十二日町、晴海の見本市に万博、いろいろなお祭りに連れて行ってくれた。けれど、父のほんとうのお祭りは夜毎始まるのだった。仕事から帰って一風呂浴びると、「さぁ、お祭りだ」父はそういっていそいそと夏ならビール、冬はお燗の用意をする。母はつまみをあつらえてくれるほど優しくはなかったので、父のつまみはきまって南京豆だった。戸棚の奥から取り出した黒光りする古い茶筒をあけると、なかにころころとよく肥えた南京豆がはいっている。わたしたちも父の膝のまわりでお相伴をしたので、父は何度も南京豆をつぎたさなければならなかった。あんなに南京豆を美味しいと思って食べたことはない。
父は夜毎のおまつりに何を思っていたのだろう。わたしは寝むまえにミルクティーをのむ。娘に淹れてもらうこともあるし自分でつくることもあるのだけれど、一杯のミルクティーがないと一日がおわらない。これは今日一日頑張った自分へのねぎらいと今日も一日しのぐことができたことへの感謝をこめた乾杯みたいなものだと思う。父のおまつりもたぶんそうしたささやかな祝祭だったのだろう・・・・父は晩酌がおわるのを待つ間もなく居眠りをはじめいつのまにか腕枕で眠り込んでしまうのだった。
クリスマスに、樅の若木を買ってくるのも、ケーキをさげてくるのもきまって父だった。両親は共働きだったけれど、暮らしはつましく母はそうした奢りはしないひとだった。あの頃はクリスマスのオーナメントも七夕飾りも花屋で売っていたのだ。てっぺんにつける銀紙とボール紙できた星、赤や白のモールのサンタクロース、金や銀のボール、毎年クリスマスが近ずくととぼしいこずかいを握り締め、わくわくしながら北浦和の花屋に走るのだ。店先で今年は何を買おうか品定めをするときのどんなにか真剣だったことだろう。
わたしにとってもっとも忘れられないクリスマスは7歳のときだった。朝、目がさめると枕もとにふたつ、深いビリジアンの細長い箱がおいてあった。包み紙はなく箱に金の文字で白木屋とかいてあった。妹とふたをあけると30センチ近い美しい人形がはいっていた。あの頃は人形といえば布とわたと針金で作られたママー人形か、セルロイドのキューピー人形しかなかったといえば、わたしたちの驚きと喜びをわかっていただけるだろうか。こんな美しい人形が自分のものになるなんて夢のようだった。前髪は巻き毛、長い金髪で瞳は青く横に寝かせると、まつげを伏せて目を閉じるのだ。わたしの人形はドレスがピンクで帽子は水色、白い靴下と白いくつ、下着も身につけていた。隣に寝ていた妹の人形はおなじものだったがドレスも帽子も赤だった。わたしと妹はルリちゃん、ルミちゃんと名づけどこに行くにも抱いていった。
後年、妹から告白されたことがある。妹は夜中に目覚め、ふたつの箱を開け、わたしの枕もとに置いてあったピンクのドレスの人形が欲しくてこっそり箱を取り替えておいたのだそうだ。ところが、朝起きたら元に戻っていたので、サンタさんはなにもかも知っていて直しに来たのだと思ってとても恐かったそうだ。戻したのは父だったのかそれとも母だったのだろうか?
四人の兄弟が成長すると、クリスマスは親からいただくというより家族のプレゼント交換の場になった。若草物語やクリスマスキャロルを読んで育ったわたしたちにはクリスマスは1年でもっとも大事な行事で、アルバイトでお金を稼ぎ、小遣いをやりくりし家族へのプレゼントをあれこれ品定めする。みんなへのプレゼントが決まるまで熱病のようにそればっかり考えていた。包み紙をといたときのみなの驚きや歓びに上気した顔が見たくて・・・・でもその年、さらったのは小学生の弟だった。わたしには陶製の青い小鳥のオルゴール、妹にはチャップリンの大きな人形、翼はすこし欠けてしまったが30年の時をくぐってオルゴールはいまもわたしの書棚の奥にある。
一昨年のクリスマス・・・・とうとう、私は夜中に目を覚ました娘に姿をみられてしまった。車のトランクに隠してあったプレゼントを運び出しているところをである。かくして去年、不況の影響もあり我が家にサンタクロースは来なかった。こどもたちにはもっともっと信じていてほしかったけれど、今年のクリスマスはむかし浦和の家で祝ったように家族でプレゼントの交換を始めるのにいい時期かもしれない。末娘がこんなことを言った。「おかあさん、プレゼントってもらうのもうれしいけど、あげるのはもっとうれしいね」
父は人形を800円で購い、それは母とのあいだでいさかいのタネとなったようだ。あの頃菓子パンが10円だったから大雑把に換算して8000円から10000円というところだろうか。でもわたしのクリスマスはあの7歳の光に充ちた朝からはじまったのだ。それがリボンをかけられきれいに包装されたプレゼントでなくても、美しいものを手にするめくるめくような喜びがあった。心にかけられいとおしまれている喜びがあった。そしてそれはひとを喜ばせ、ひとを幸せにするというたぶん人生で一番の幸せを知ることにつながっていった。それが父がわたしにくれた最大のプレゼントだったような気がする。
14/1/18