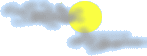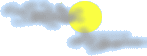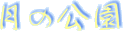
友人のOが「金沢大を受験するから金沢までつきあってくれないかな」と言うので、ついて行くことにした。高校を出てからフリーターをしながらフラフラしていたわたしたちも今年は24になる。お見合いをして結婚するか、就職して身を固めるか、かれこれ年貢の納め時だった。70年安保の敗北、そして浅間山荘事件に続くわたしたちの世代の闘争の変容は微かな希望を微塵に砕いた。といってもわたしは想像のなかで石を握り締めるのが精一杯のノンポリにすぎなかったのだが。世界は変わりようもなく愚かな人間の愚かな歴史は繰り返されるだけだ。動くのも大儀な倦怠感のなかでわたしはなんの希望もなくただ息をしていた。何もなしえず何者も幸福にできない自分がただ重かった。道路を歩きながら空からの落下物が、暴走するトラックが自分の躰を圧し潰すシーンを飢えるように夢見ていた。バスや電車の車内で罪や咎のしみついた人々の顔を見るのが怖くて固く目を伏せていた。私は、軽いノイローゼになっていたのかもしれない。
オーストラリアからの帰国子女、佳ちゃんの家庭教師の後任を喫茶店で偶然あった大学生に押し付けると私はもう自由だった。その大学生は人は良いけどいい加減なやつだってわかってはいたのだ。佳ちゃんの母親に挨拶をしながら私は心のなかで詫びた。
豪雪で列車が動かないので、急遽羽田から小松空港に向かう飛行機に乗る。小さなプロペラ機の主翼のビスは気流の変化でガタガタ震え、今にも飛びそうだ。それを私は丸く穿たれた窓から見るともなく見ていた。小松空港から金沢市内に行くバスから眺めるのは一面の雪景色だった。兼六園に面した小さな清潔なホテル、一服する間も惜しんでOは明日の試験会場の下見に出かけた。私もあとを追うようにちいさなバックをひとつ抱えて外に出る。金沢駅から列車に乗る。
黄ばんだ侘しい日本海の夕暮れのなかを列車は走る。車窓が闇に包まれ、人影もまばらになった頃、なにかに促されるように列車を降りる。駅を出ると積もっているはずの雪がない。内心うろたえるが、戻っても仕方がないと諦めて歩く。街の中心からはずれて、郊外をどのくらい歩いただろう。繁みに隠れるように石造りの急な階段が目につく。昇っていくと突然視界が開ける。山の中腹を切り取った公園だった。月の光に、融け残った雪が白く光る。ここでいい、わたしは雪のうえに坐り、バックから薬壜を取り出して膝の上に並べる、そしてひと壜ずつ錠剤を飲み下し空にしてゆく。空き瓶をバックに戻し雪の上に横たわって足を伸ばす。怖れもなく悲しみもなく後悔もない。満月に近い月が冴え冴えと地の上を照らし、上空では風が強いのか、むらくもが飛ぶように迸ってゆく。ほどなくわたしは意識を失う。
覚醒は突然きた。わたしは歯の根も合わぬほどガタガタ震えていた。失敗した。絶望が私を凍らせる。みっともない、どうしよう。はるかに貨物列車を送るレールの軋む音が空気を振るわせる。ロープはどこかにないか、目まぐるしく巡る思考の核にぽつんと熱く固いものがある。そして、それは膨れ上がり、火、熱、温もりを求めてわたしはフラフラ立ち上がり、歩き出す。もう迷いはない。灯りがともり、火のある場所ならどこでもいい、凍りついたアスファルトにコツコツ足音が響く。町は寝静まっていて犬さえいない。目当てもなく遮二無二歩いていると、啓示のように電柱にユースホステルの黄色の看板が張り付いている。路地に入ってゆくと、民間のユースホステルなのだろうか、一軒の玄関の前に私は立っていた。
「ごめんください。」最初は恐る恐るそして祈るように声をかける。灯りがついておじいさんが、陰にかくれるようにおばあさんが姿をみせる。「こんな時間にすみません。泊めていただけないでしょうか。」おばあさんは泊めたくないそぶりをする。絶望が私を噛む。夜明け近く、若い女が蒼白の顔で髪を乱してやってきたら、誰だって巻き込まれるのは厭に決まっている。そのとき、おじいさんが「どうぞ、おはいりなさい」といってくれる。おじいさんが沸かしてくれた熱いお風呂、檜の湯船のなかで冷え切った躰にお湯が刺すように痛かった。お客は他にいないようだった。示された二段ベッドの、冷たい真っ白なシーツの間に夢もなく私は眠った。
翌朝、おじいさんは何もたずねなかった。私も何もいわなかった。別れの時おじいさんは「あんじょうおしゃっしゃ」といって玄関から送り出してくれた。それは年若いわたしに人生の旅の平安を祈る餞のことばだったのだろう。わたしは振り返って頭を下げた。来る時には気がつかなかった路地の生垣の緑の葉が艶やかに光っていた。
駅につくと幾人も弁当売りやお茶売りが旅行客を待っていた。背の低い眉の濃いおじさんからわたしはお茶を一瓶買って、その場でごくごく飲み干した。美味いお茶だった。躰にしみとおるお茶だった。「あんたは美味そうにお茶を飲むね、俺の淹れるお茶は駅で一番美味いんだよ。もう一杯飲みなよ、代はいらないよ。」わたしは有り難くいただいた。こうして冬の能登から、私は生還したのだ。
その年わたしは、父母の庇護する屋根の下を父母の反対を押して出た。そののちわたしは、日本海の絶壁から身を躍らせるように無謀な選択をいくつかした。サルトルのいうようにアンガジュマンし大江のいうように見る前に跳んだ。自分でとった行動で起きることはすべて、自分で引き受けるつもりであったが、そんな思いには関わりなく、またすべてを隠しおおせることもできずに両親を深く悲しませてしまったこともある。しかしそれなくては生きてゆけない、わたしの究極の選択でもあったのだ。
今にして知る。あの夜、月の光射す公園で、わたしの一部、一番やわらかくすき透ったところは、間違いなく死んだのだった。生きるために必要な少しの強靭さと引き換えに。今も、どことも知れぬ月の光の公園で薄青い透明なわたしの影が行き場なく彷徨っている。そんな気がする。