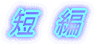
 

一週間降り続いた雨がようやくあがった。
クロヒコはひさしぶりに班の連中六匹を率いて、巣穴の外へ出た。もちろん餌を探すためだ。クロヒコたちの担当区域は校庭のブランコ方面だった。
「梅雨でもないのに七日も降り止まないとは参ったね。こんなに雨の多い夏は聞いたこともないよ」
クロヒコは班の若いアリたちにもっともらしく話して聞かせた。
クロヒコが成虫として夏を迎えるのはこれが二回めだ。若いアリたちは一回め。その程度の違いでしかない。だが、アリにとっては、一回めと二回めの違いは大きかった。
ついでに言うと、男のような名まえがついているが、クロヒコは雌だ。巣穴でほんとうに女らしいのは女王アリただ一匹で、ほとんどがクロヒコのような働きアリだった。働きアリがおしとやかにふるまっていたのでは餌は集まらない。クロヒコは自分を雌だとか雄だとか考えたこともなかった。
餌探しの一行は訓練された足どりできびきびと地面を這っていった。クロヒコたちの巣があるのは小学校の給食室の裏だった。ふだんは食べ物のかけらが落ちていることが多い。だが、今のような八月のさなかはてんでいけなかった。クロヒコは少しばかり遠出をすることにした。
古いイチョウの木の近くまで行ったとき、先頭のアリが号令をかけた。
「ぜんたぁい、止まれ! 一、二、三、四、五、六」
アリたちは六本の足をぴたっとそろえて止めた。その目の前に大きな餌が横たわっていた。アブラゼミの死体だ。
「こいつはいい。当分の間の食糧になるぞ」
クロヒコは大股に歩み寄ると、触角でとんとんとたたいてみた。まだ新鮮な死体だ。
「セミの皮って、甘味があってぱりぱりっとしてて、おいしいんですよね、班長」
副班長のツブラがクロヒコの後ろでたまらなさそうにごくっと喉を鳴らした。
クロヒコは班員たちの方を向き、さっそく指示を与えた。
「七匹で運ぶのはとうてい無理だ。だれか一匹、巣穴にもどって応援を呼んで来な。その間に残りの者はよその巣穴の連中やほかの生き物なんかに餌を奪われないようにしっかり見張っておくとしよう」
一匹が匂いのする液体を地面に噴きかけながら去っていった。この液体は同じ巣穴の仲間だけが作ることのできる特製の香水で、あとで仲間が引き返してくるときの道しるべになるのだ。残った六匹は餌を真ん中に囲み、応援が来るのを待った。
真夏の日射しがクロヒコたちの黒い背中に照りつけた。あちこちの木々からセミの鳴く声が響いた。いかにも夏らしくて、クロヒコはこの声を聞くのが好きだ。雨が続いたあとではなおさらそうだった。
「……晴れて、いるのか?」
ふいに、間近で声がした。かすれた弱々しい声だ。クロヒコはきょろきょろ辺りを見回した。班員たちのほかには誰もいない。
「おい、今、何か言ったか」
クロヒコはツブラに聞いてみた。
「言いませんよ、なんにも」
ツブラはきょとんとして答えた。
すると、今度はもっとはっきりした声が聞こえてきた。
「仲間たちが、鳴いている……どうやら、雨は、やんだのだ……」
「げっ。餌がしゃべったぁ」
ツブラは叫んでひっくり返った。パン屑が口を利いたのと同じくらいびっくりしたらしい。
「あわてるな。この餌はまだ死んでいなかったのだ。それだけのことだ。弱っているから、どうせ逃げられはしない」 クロヒコは先輩らしく落ち着いて、うろたえる班員たちを鎮めた。
地面に仰向けに転がっていたセミは、そばに虫がいるのが分かると、ばたばた足を動かした。
「み、水をくれ……たのむぅ」
セミ族の訛りのある昆虫語で、セミはあえぎながら訴えた。ツブラとほかのアリたちは顔を見合わせてもじもじした。
まずい、とクロヒコは思った。若いアリたちにとって、まだ息のある餌というのは刺激が強すぎて危険だ。なにしろ同じ昆虫語をしゃべるのだ。餌だということを忘れて、つい同情してしまう。
クロヒコは班員たちにぐるりと周りを見張らせておいて、自分だけがセミの側に残ることにした。
「悪いけど、セミさん。あんたはこれから餌になるんだ。水なんか欲しがらずに、さっさと死んだほうが楽だよ。わたしたちだって、生きている昆虫の体をちぎって運ぶのはいやだからね」
「あんたたちは、アリか……?」
弱っているために目が見えないらしく、セミは尋ねた。
「そうだ。わたしはクロヒカリ女王国の餌収集団、発見隊第五班、班長クロヒコ」
「おれは、……」
セミは名乗ろうとして、ぜいぜいと息を切らした。クロヒコはすばやくさえぎった。
「名まえなんか聞きたくない。餌に名まえはいらないよ。言うまでもないけれど、生き物はみんな時が来れば死んでいく。あんたも例外ではなかったというだけさ。│ほら、聞こえるだろう。若いセミたちが鳴いている。あんたの時代は終わったんだ。あきらめて、いさぎよく往生しな」
「おれの時代は、雨だった」
セミはつぶやいた。
「暗い土の中で、数年間の幼虫暮らし。やっと成虫になるときがきて、地上に出た。それが、長い雨の降り始める四日前の夜だった」
「そうか。あんたたちセミはお日さまのもとで十日かそこいらしか生きられないのだったな」
クロヒコはうなずいた。何年も生きるアリに比べて、なんてはかない命だろう。
「おれの身の上を聞いてくれないか。この際おれを食ってしまうやつでもいい。死ぬ前に昆虫と話をしたい。話しておきたい」
セミは体をよじって頼みこんだ。
あまり気は進まなかったが、クロヒコは好きなようにさせてやることにした。
「いいだろう。仲間が来るまで何もしないで待つのは退屈だ。聞いてやるからしゃべるがいい。ただし、仲間が駆けつけたらその場で話を打ち切り、餌として処分する。そのつもりで覚悟しておけよ」
「ああ」
セミは大きく息をついて、絶え絶えに語り始めた。

その日、夕焼けが色あせ、星が光りはじめたころ、おれは地上に這いあがった。大きな生き物に食われることもなく、餌不足で死ぬこともなく、無事に成虫になる日を迎えたのだ。おれは一番近くにあった桜の木に上ってここで幼虫の殻を脱ぐことにした。
幹につかまり背中にうんと力をこめると、ぱりっと殻に割れ目がはいった。足で支えながら体をぐっとそらし、頭から腹まで、すっぽりと殻を脱いだ。縮んだ羽が力強く伸びていくのが分かる。やったぞ、成虫になれたんだ。
おれはさっそく桜の幹にストローを刺して、甘い汁を飲んだ。幼虫のとき土の中で吸った根っこの汁よりもこくがあってうまかった。
それから三日間は気ままな若者時代を楽しんだ。そして四日めの朝、おれはふいに大声で鳴いてみたくなった。これは一人前のセミとしての心構えができたってことだ。
とりあえず、近くのイチョウの木にとまった。そう、ここに生えている、このイチョウだ。おれは力をこめて鳴きはじめた。
ミーン、ミンミンミンミンミン……
――おいでよ、おいでおいでおいで。ここだよ、ここだよ、ここにいるよ……
もちろん雌を呼んでいるのさ。鳴き声にひかれて雌がやって来たら、おれたちは結婚する。短いセミの一生では何より出会いが大切だ。一匹の雄と一匹の雌が一本の木の幹でめぐりあう。これは大変な出来事だ。おれにとって彼女はかけがえのない雌だし、彼女にとっておれはかけがえのない雄だってことになる。
ミーン、ミンミン、ミーン、ミーン……
――おいでよ、おいでよ。ここだよ、ここだよ。ぼくはここにいるよ。
昼過ぎころから空気が生温かくなった。空の色がよどみ、厚ぼったい雲が垂れ下がった。雨だ。乾いた地面に水玉が散った。地面はたちまちずぶぬれになり、低いところに向かって水が流れ始めた。
おれは幹に止まって、じっと降り止むのを待った。
その日、雨は止まなかった。日が暮れ、夜が過ぎて、また日が昇った。
昇った太陽は見えなかったけれども、うす明るくなったので、朝とわかった。だが、晴れた日のような本物の日射しはなかった。雨は降り続いていた。おれは幹に止まって、寒さに震えながら雨が止むのを待った。
その日、雨は止まなかった。
明くる日も、夜明け前から雨が降り続いた。おれは将来のことが不安になりはじめた。このままでは思う存分鳴くことができない。雌とめぐりあうこともできない。
おれは試しに呼んでみた。
ミーン、ミンミンミンミン……
――おいでよ、おいでおいで……
雨の音がおれの鳴き声をかき消した。声はそのまま消えていくだけだった。
かりに、おれの声が聞こえたとしても、雨の中を外の木から飛んで来る雌がいるはずはなかった。羽が濡れて動けなくなり、雨に叩き落とされてしまうだろう。
おれは鳴くのをやめた。
その次の日も、まだ雨は降り続いていた。おれは焦り始めた。このままでは独り寂しく年を取るばかりだ。どこでもいい、仲間のいるところへいきたい。
近くの木を目指して、おれは雨の中に飛び出した。ぽたっと雨粒が背中を打った。羽が水を含み、しめって動かなくなった。続けざまに雨が背中を打ちのめした。
おれはくるくる回って地面に落ちた。うまいぐあいに太い枝の真下だった。枝と葉っぱが雨を防いでくれた。おれは這いつくばって木の根元に帰った。背中がじっとり濡れて気分が悪かった。羽が開かないので、まるで幼虫のようにぶざまに幹をよじ登らなくてはならなかった。
次の日になっても、まだ雨は降り止まなかった。おれはやけくそになって空にわめいた。
「なるようになれ。降りたいだけ降るがいい」
すると、まるでそれに応えるかのように、雨はますます激しく叩きつけてきた。
おれはぶるっと震えて、幹にしがみついた。いくら長い雨でもいつかは降り止むと聞いている。四日も降り続いたのだから、もうそろそろ止んでもいいころだ。それなのにいっこうに止みそうにない……。
その日もやっぱり雨は降り止まなかった。日が暮れ、夜が過ぎて、また日が昇った。
雨垂れは枝や葉の透き間をぬい、幹を伝っておりてくるようになった。おれは濡れないためにたびたび場所を移動した。
「やんでくれ。早くやんでくれ。今すぐにやんでくれ」
おれは天に向かって泣かんばかりに叫んだ。一日一日、おれは年を取った。残された時間はもうあまりなかった。
こうなったら雄でも雌でもいい、同じセミ族と語り合いたいと思った。
「誰か来てくれ。答えてくれ」
ミーン、ミンミンミンミン……
おれは鳴き続けた。誰かが答えてくれると本気で思った訳ではない。ただ、鳴かずにはいられなかったのだ。おれは雄のセミに生まれた。雄のセミはまぶしい夏の光のもとで、思う存分鳴くものだ。まぶしい夏の光はなかったけれど、おれは思いっきり鳴きたかった。
ミーン、ミンミンミンミンミーンミンミンミーン……
――ここだよここだよ、ここにいるよ。ここだよ、ここだよ、おれはここにいるよ。ここで生きているよ。いま生きているよ。いまも、いまも、いまも生きているよ……
ミーンミンミン、ミン、ミンミンミンミーン、ミン……
おれは何日も雨の中で鳴き続けた。頭の中は空っぽだった。鳴いている間は神経を打ちのめすすさまじい雨の音も、聞かないですむ。
ふと、おれのものではないセミの声が、空っぽの頭に響いてきた。
ミーンミンミン、ミンミン……
――いるよ、いるよ、ここにいるよ。ぼくだ、ぼくだ、ぼくだよ。
――どこだ、どこだ、どこにいるの?
――いるよいるよ。ここにいるよ。
いくつものセミの声だ。おれの仲間たちの声だ。
ミーンミンミン、ジジジジジ……
――ここにも一匹、セミがいるよ。たった一匹セミがいるよ。独りぼっちのセミだよ。
――独りぼっちはここにもいるよ。独りぼっちがたくさんいるよ。
――友達。仲間たち。あっちこっち。
――見えない、聞こえない。でも、感じるよ。
――聞こえない、知り合えない。でも、いるんだね。
おれたちの鳴き声は歌だ。情熱をこめた詩だ。心を揺り動かす力はもっているが、こみいった思いを伝えるのには向いていない。ひとしきり鳴いたあと、おれたちはふだんの話言葉で呼びかけあった。
ジジ、ジジジ……ジジジジ、ジ……
――悪い時代に生まれちゃったね。
――ぼくたちのせいじゃない。
――思いっきり鳴いてみて、よかった。
――セミは思いっきり鳴くものさ。
疲れ果てるまで鳴き続け、休んではまたうたい、おれは時間を忘れた。おれの心には聞こえていた、仲間たちの鳴く声が。今もどこかの木で、誰かが、おれといっしょに鳴いている……
やがて、幹につかまる足の力が弱り始めた。
――どうやら、ぼくはもうじき死ぬ。
――そろそろ、ぼくも、いけないようだ……
――ぼくは、もう、落ちそうだ……あッ。
――さようなら、さようなら、仲間たち。
ミーン、ミンミンミン、ミンミンミン、ミンミン……
仲間のセミの声が一つ消え、二つ消え、おれの頭の中は再び空っぽになった。おれは幹からぽろっと外れて落ちた。そのあとのことは、もう覚えていない。

セミは語り終えた。
いつのまにか、見張りをさせておいたはずのツブラがすぐそばに来て、熱心に話に聞き入っていた。
「気の毒なセミ。ああ、どうしよう。わたし、セミの皮のぱりぱりっとしたところが大好きなのに、とっても食べる気になれないわ。すごく残酷みたいに思えるんだもの」
クロヒコはあわててしかった。
「見張りはどうしたんだ、ツブラ。勝手に持ち場を離れたりして。副班長がそんなことでは班員にしめしがつかないじゃないか」
「だって、班長」
「餌というものは、まずいかうまいか、栄養があるかないか、どちらかなんだ。気の毒な餌なんてものはないんだ。このまま放っておけば腐るしかない死体を、巣穴で待っているかわいい幼虫のために役立ててやるんだから、少しも残酷なことはない。それが自然界の決まりってものだよ」
「わかりますよ。それはわかっているんだけど……生きている間はやっぱり、餌ではなくて、虫ですよ。虫としての命の尊厳は無視できません」
「おだまり、ツブラ。難しい言葉を使ってみせてもだめ」
クロヒコはセミのほうに向き直った。少しためらってから、クロヒコは尋ねた。
「セミさん、あんたの名まえは?」
「セ、ミ、イ、チ……」
身の上を語ることで体力を使い果たしていたセミは、しゃがれた声で、やっと答えた。
「セミイチさん。まだ生きているのに餌にして、気の毒なことだったね。でも、仲間に呼び出しまでかけたからには、あんたが自然にくたばるのを待ってはいられないんだ。すまないけど、命をもらうよ」
同じ巣穴の仲間たちが合図に使っている香水の甘酸っぱい匂いが漂ってきた。巣穴のある方角から仲間たちが行列を作ってやってくるのが見えた。先頭は、さっき巣穴に知らせに戻ったクロヒコの班のアリだ。
「班長、運送隊と処理隊から五十匹が応援に駆けつけてくれました」
班員のアリがクロヒコの側にやって来て、報告した。
「ご苦労。では、さっそく……」
クロヒコは大きなセミの体を見上げた。セミイチはもう触角一本動かさなかった。ただ、死んではいない徴に、かすかに息をついているのがわかった。
処理隊のアリたちはセミの体によじ登った。このままでは大きすぎるので、巣穴に入るくらいの大きさに砕いて運ぶのだ。処理隊の隊員はこの手の作業には慣れていた。
「しばらく待て」
作業が始まろうとする寸前、クロヒコがふいに声をかけた。処理隊のアリたちはけげんそうにふりかえった。
クロヒコは視線を落として言った。
「もう、ほとんど死にかけている。静かに死なせてやれ」
そう言いながら、クロヒコはセミイチの耳元に近づいた。もう聞こえないかもしれない、と思いながらもクロヒコはささやいた。
「セミイチ。お体を、受け取らせていただきます」
クロヒコは餌に頭を下げた。
――どうぞ、ゆっくり休んでください、セミイチ。
ジジジジ、ジ……と、セミは答えた。
一週間ぶりの太陽が、校庭のイチョウの木のもとに、一週間ぶんの日射しをふりそそいだ。
アリたちに囲まれて、セミイチは息をひきとった。
(終わり)
1990年ころ創作、後年職場の文芸同人誌「シソーラス」に掲載
|