|
「本が好きだもん」 試読編 試読編
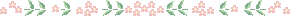
「物語工房」の管理人は、隔月1回、本についての個人情報紙「本が好きだもん」を発行しています。こちらは、その中から一部分を試し読みしていただくコーナーです。
「本が好きだもん」の刊行は、2008年1月の29号でいったん終了しました。いつか復活することがあるかもしれませんが、近いうちではありません。
経緯については、2008年1月4日の「工房日誌」に書き留めました。
後日、これまで発行した創刊号〜29号までのデータをまとめようと思います。
2008年1月3日発行 第29号から抜粋(1件)
あさのあつこ『バッテリー』シリーズ
〔教育画劇 → 角川文庫〕
こちらも(註:その前の段で「守り人」シリーズについて言及している)初巻から数年をかけて完結した大作。作中に流れた時間は一年ですが。
初めて第一巻を読んだときには、新しいタイプの主人公の登場がひたすら新鮮に感じられました。第二巻では中学生活が始まり、校則だの、教師だの、クラスメイトだのが描かれ、読者の私としては「そんなのどうでもいいから野球に専念しようよ。ごちゃごちゃ面倒くさいよ」と、まるで主人公の巧のような感想を持ちつつ読んだものです。でも、この巻から、天才野球少年の野球の道を書いただけの作品ではない、という方向性が見えてきたようにも思います。
初読の時に一番好きだったのは第三巻の紅白戦でした。脇役であった少年たちの個性が鮮やかに見え、どの子も面白くて素敵で、早く完結編を読みたい、だけど、いつまでもこの作品を楽しみたい、という矛盾した願望を持ちました。
ところで、第四巻からあと、私は初めのころほど熱心な読者ではなくなっていました。登場人物が饒舌になり、本筋に関係すると思えない軽口や冗談で紙面が埋め尽くされ、作風が変わってきたのかなあと、ぼんやり感じました。逆に「第四巻から、あさのあつこは本格的な作家になった」と評価している人もいて、いつか読み返して、その文章を……とくに文章の力と書きぶりを確認してみたいと思っていました。
今回、数か月のうちに第一巻から第六巻までを文庫本で読み通してみて、(初版の文章に加筆があるとしても)、確かに自分の読み方は浅かったと感じます。とくに、最終巻は登場人物たちの饒舌さも含めて上向きに受け止め直しました。この作品は、野球の天賦の才能を背負った(敢えて「背負った」と表現します)少年とその相棒の物語として始まり、チームメイトとして天才を身近に置くことになった少年たちの、それぞれの物語として完結したのだ、と。
2007年1月27日発行 第26号から抜粋(1件)
上橋 菜穂子 作
『獣の奏者』1闘蛇編、2王獣編(講談社)
上橋菜穂子の新作。人気の「守り人」シリーズ(偕成社)は十年の年月を重ねていよいよ最終巻を目前にしていますが、こちらは全く新しい世界を描いたファンタジーです。
主人公のエリンは、母親と二人で暮らしている十歳の少女。しかし、獣ノ医師である母は戦闘用の闘蛇が何頭も死んだことの責任を問われ、処刑されてしまいます。
この地球上の地理にはない国で、我々の世界には存在しない生き物がいるということを除けば、極めて現実的な事件や日常が展開されます。架空のファンタジー世界を作り上げるとき、とかく西洋風の世界になる傾向があるようですが、この作者はどこか東洋的な匂いのする、固有の歴史や文化があざやかに浮かぶ国土を創造しています。
愛読者としてとても欲張ったことを言うならば、急いで出版することなく、もう少し練りこんでから世に出してほしかったと思います。ところどころで、あとの展開のために準備されたことを意識してしまう伏線が目につきました。周到に作られている、という印象がつきまとってしまいます。その一方で、重要そうに見えながら、あまり書き込まれていない登場人物もいます。もちろん、これらは欲の深い注文であり、期待度の低い作品ならば気にしない事柄です。
人と獣の間に生まれる絆と、なおも存在する隔ての大きさが、ここまで深く掘り下げて語られることに感銘を覚えました。途中からは結末を予想しつつ読みましたが、作者が選んだラストシーンは、予想を超えて感動的なものでした。作中に盛り込まれた世界観、人間観、人生観には、一片の不快さもありませんでした。
〔タイトルのローマ数字をアラビア数字に置き換えています。〕
2006年11月24日発行 第25号から抜粋(1件)
中澤 晶子 作/北山 斗志 絵
『デルフトブルーを追って』(国土社)
祖父の家の蔵に一枚だけ残っていた青いアサガオの絵皿。そっくりの絵皿がオランダの焼き物の街デルフトで見つかりました。ヒカルの両親はその謎を解こうとした矢先、交通事故で急死します。ショックで声を失ったヒカルは、叔父とともに絵皿の謎を追って、デルフトに旅立ちました。やがて、少年イアンが見つけた先祖の手記を通じて、三百五十年前の絵皿をめぐる縁が、明らかになっていきます。
江戸時代の少年陶工たち、居安(いあん)と光太郎の物語だけで姫谷焼にまつわる歴史ものを書き上げることも可能だったでしょう。けれども、現代と過去、日本とオランダの二組の少年の物語が交差することで、短いのに壮大な物語を読んだような満足感がありました。
姫谷焼についての新聞記事を見つけてから十二年。年月をかけ、取材を重ねた作品ならではの厚みが感じられ、じっくりと作品の完成度を上げていく作者のこだわりが、心ゆくまで青の色合いにこだわる陶工たちの思いに重なりました。
2006年9月21日発行 第24号から抜粋(2件)
菅野 雪虫 作
『天山の巫女ソニン1 黄金の燕』(講談社)
赤ん坊のときに巫女になるために天山に連れて行かれ、十二歳で見こみなしとして家に帰されたソニン。そのまま平凡な人生を送るはずだったのに、ふとしたことから王子に仕えることになり、陰謀に巻き込まれて、波瀾万丈の日々に見舞われます。
舞台は三つの国が分立する半島の国ですが、固有名詞からも地形からも、韓国・朝鮮のことと分かります。ただし、それは百済や新羅のように実在した国ではなく、あくまでもコリア風ファンタジーの世界です。
世俗の汚れにも染まるのでもなく、天山の巫女のように世俗と無関係に生きるのでもなく、前向きに自分の人生を歩んでいくソニンの描き方に、温かな作者のまなざしを感じます。世界観よりも世間観(こんな言葉はないけれど)に注目したい作品だと思います。脇役たちの語るさりげない人生訓は、作者の説教としてではなく、苦労人による味わいのあることばとして、心地よく耳を傾けることができました。
全編を通して、平凡な素材と手法を磨きぬき、平凡なまま極致まで高めたという印象を受けました。デビュー作ながら、既にシリーズ化が決定しています。
M・W・ターナー 作
『盗神伝』4・5(あかね書房)
これまでに三巻が刊行されている『盗神伝』シリーズの新刊「新しき王」。その前篇となる第四巻は「孤立」、後篇の第五巻は「栄光」と題されています。
われわれ読者はここまでの巻で有能な盗人としてのジェンを知っているわけですが、この巻では新しく登場する人物たちの目に映った奇妙な王として語られていきます。
相変わらずの面白さで、夢中になって読みましたが、読み終えた後で『盗神伝』がここを分岐点として別の作品になってしまったような喪失感を覚えました。これはもう盗人の物語ではないのかも知れません。ここからもっと大きな物語が語られていくのでしょう。でも、それは初めに出会った『盗神伝』とは違うような気がします。
〔タイトルのローマ数字をアラビア数字に置き換えています。〕
2006年5月24日発行 第22号から抜粋(1件)
エミリー・ロッダ 作
『デルトラ・クエスト』シリーズ(岩崎書店)
(1・2 岡田好惠・訳/3 上原梓・訳/全巻 はけたれいこ・絵)
全十五巻に及ぶ三部作が完結しました。
最初にシリーズ(1・全八巻)の存在を知ったときには、「ローワン」の作者が書いた新作ファンタジーとあって、大いに期待して読み始めました。しかし、「ローワン」にくらべて浅い内容、平板な人物像、「ゲームよりもおもしろい」といったキャッチコピーのありかたに、かなり失望したものでした。
しかし、読み進めるうち、べつの面白さを感じるようになりました。まず、作者のテクニック。とても巧い書き手だと思います。残りページが少なくなって、いったいこの巻で結末がつくのだろうかと危ぶんでいるうちに、あっと驚く解決の糸口が見つかります。あまり長くない物語の連作で、一巻ごとにわかりやすい結末が用意されており、しかも全体を通して意表を突く展開があることも、読者を惹きつけているのでしょう。
たくさんの人物や事柄が登場して、それがまた先の巻や先のシリーズで再登場するので、図書館で間隔を置いて借りている私は、たびたび「この人誰だっけ」という状態に陥りました。伏線がいっぱい張ってあるのですが、全ての巻を手元に置いていないと、なかなか全部を確認できません。それは「少し読み足りない」、「また読み返したい」というやみつきの感覚に導かれます。巨大なテーマパークに行って、遊び尽くさずに帰るような感じです。
さすがに「ローワン」の作者だと感じる場面もありました。敵同士としてにらみあってきたキンと小人族の共生のあり方などからは、『ローワンと黄金の谷の謎』(あすなろ書房)の世界観を思い起こしました。
最近では、『フェアリー・レルム』(童心社)のシリーズが快調です。ほかに、『ティーン・パワーをよろしく』シリーズ(講談社)、『ふしぎの国のレイチェル』(あすなろ書房)などが刊行されています。(私は「ローワン」に次いで「レイチェル」が好きです)
〔文中、ローマ数字をアラビア数字に置き換えています。〕
2006年3月19日発行 第21号から抜粋(1件)
ラルフ・イーザウ 作/酒寄 進一 訳
『暁の円卓』全九巻(長崎出版)
巻末にある「訳者あとがき」によると、作者がこのシリーズを構想したのは地下鉄サリン事件の報道を見たのがきっかけで、原書の第一巻が刊行されたのは一九九九年、最終巻の刊行は二〇〇一年九月(同時多発テロの直前)だということです。非常に短い期間にこれだけの長編が書き上げられていることに驚嘆しました。
この作品を一言で表すなら、戦争を始めとする二十世紀の忌まわしいできごとを振り返り、それを悪の親玉が仕組んだ一連の計画と位置づけて、正義と悪との戦いというファンタジーに組み直したものです。
創作で世紀を語るという構想を知ったときには、その試みにかなり興味をかき立てられました。全巻を読み終えた今は、〈賞賛〉と〈非難〉の気持ちが入り交じっています。
〈賞賛〉とは、言うまでもなく膨大な資料を集め、詳細に読み込み、これだけの壮大な長編にまとめあげた技とエネルギーに対するものです。何はともあれ最後まで飽きずに読み通せたのだし、日本について書かれた箇所も大部分は違和感なく読めました。最終巻ではビン・ラディンのことに触れられていますが、原稿が書かれた時期を考えると、そのアンテナの感度に敬意を表します。全編を通じて示された偉大な実験精神に対しても。
ただし、エピローグで語られる結末は無理をしすぎていて、ついていけませんでした。こういう極端な結末の付け方を頭から否定するものではありませんが、読者に納得させるにはもっと全精力を傾けるべきです。それでなければ、たとえ相対性理論の名を持ち出そうと、ただの陳腐なご都合主義です。
さて〈非難〉の部分です。現実にはばらばらに起きているさまざまな事件や現象を、あれもこれも悪の結社が計画したものとして結びつけてしまうのは、いかにも「絶対悪」と「絶対的正義」の対決が好きな欧米人らしい設定です。私の趣味には合いませんが、これはこういう物語なのだ、という約束事を受け入れるとしましょう。ただ、物語の随所で「現実に起きた厳粛なできごとを、こんなにも軽々しくもてあそんでいいものだろうか」という疑問を感じてしまいました。ことに近代のできごとを扱うときには、遺族や関係者の心情にもう少し思いやりがあってもいいのではないかと……、とりわけ作者にとっては遠い僻地なのであろう、アジアのできごとに関して思いました。
例を挙げれば、愛国心から暗殺行為に出た安重根を、欲に駆られたけちな小悪党に仕立てるのは名誉毀損ではないでしょうか。義士と讃えるにしろ、結局は人殺しだと責めるにしろ、その動機は純粋なものであり、悪の手先ではありません。地下鉄サリン事件も東海村の臨界事故も、被害者にとってはまだ生々しいできごとです。気軽にネタ(敵の計画の一部とか…)にしてほしくありません。
また、ヒロシマのことは一応、大きな災厄として語っているようではありますが、別の箇所(第九巻)で問題解決のために主人公が核爆発を利用するというストーリーを持ってくるとは、どういう神経なのでしょう。アメリカの西海岸で爆発するのは悪くても、太平洋上ならかまわないだろう、と錯覚しているようです。この作者は歴史上のパーツをつまみあげて器用に組み合わせるけれども、物事の本質がちっとも分かっていない人なのだと憤りを感じます。
今世紀はさらに戦争とテロの頻発する時代になりました。地球の未来は一つの悪の結社や一人の極悪人、ましてや一人の〈世紀の子〉の存在に左右されるものではありません。
2006年1月24日発行 第20号から抜粋(1件)
バーナード・アシュリー 作/さくま ゆみこ 訳
『リトル・ソルジャー』(ポプラ社)
アフリカの都市ラサイで、内戦の少年兵として戦ってきたカニンダ。殺された家族の復讐をすることしか考えていない彼でしたが、不覚にも赤十字に保護されてしまい、ロンドンの里親の下に引き取られていきます。ところが、同じ学校に、敵の民族の少年が転校してきて……。
読み始める前に、書評などでおおよその設定は知っていました。だから、人が争うことのむなしさを説き、「人類はみな兄弟、仲良くしましょう」といった意味のことが真っ直ぐに謳われるのだろうと想像していました。
こういう言い方をすると意地悪な気持ちで見ているみたいですが、それはそれで感動的であり、良心的な物語が展開していくのだろうと期待していました。
ところが、物語は大いに回り道をします。ロンドンの不良少年(少女を含む)グループの抗争が語られ、里親の娘ローラの過失と罪の意識に大きくページが割かれます。
いったいこれは何をテーマにした話なのかと思っているうちに、結末は急展開、ずしりと重いものが残りました。
理不尽な内戦は、ラサイにもロンドンにもありました。自分が渦中にあるときはなかなかその理不尽さが見えませんが、よその集団がやっている抗争のばかばかしさは、とても分かり易いものです。
2005年11月23日発行 第19号から抜粋(2件)
ロニー・ショッター 作/千葉 茂樹 訳
『秘密の道をぬけて』(あすなろ書房)
アメリカに奴隷制度があったころの物語。易しい文章に豊かな内容が無理なく詰まっていました。
主人公のアマンダは十歳。ある夜、物音に目を覚ました彼女は、両親の秘密を知ります。そこからアマンダは逃亡奴隷を逃がす非合法組織「地下鉄道」の一員としての役割を果たすことになります。逃亡する一家の中には、同い年のハンナもいました。
真面目に言えば「逃げる側とかくまう側の少女の交流を通して、人間の尊厳や自由の意味が謳われた作品」だと思いますが、追っ手との駆け引きや逃避行はどきどきする冒険譚のようにも読めて、読者を飽きさせません。
作中、アマンダがハンナに字を教えようとする場面がありました。フランチェスコ・ダダモの『イクバルの闘い』(鈴木出版)にも、じゅうたん工房で奴隷のように働かされている子どもたちが、こっそりと字を覚える場面がありましたが、読み方を知ることは自由への入り口なのだと再確認させられました。
セリア・リーズ作/亀井よし子 訳
『レディ・パイレーツ』 (理論社)
貿易商の娘ナンシーは、亡き父によって血も涙もない中年男との婚約を決められ、さらには兄たちの裏切りによって窮地に立たされます。ナンシーは友達になった奴隷の娘ミネルヴァとともに、追っ手から逃れて、海に乗り出しました。
少女の生き方にアヴィの『シャーロット・ドイルの告白』(偕成社)と通じるものを感じました。ただし、私は『シャーロット・ドイルの告白』の方がより好感を持って読めました。ナンシーが難なく肉体労働に従事できるところは違和感があります。結末の付け方も『シャーロット』のほうが好きでした。
そうは言っても、この『レディ・パイレーツ』もかなり読み応えのある作品でした。海賊の物語とはいいながら、奴隷貿易やプランテーションや海の労働についても描かれ、エンターテイメントの要素とまじめな歴史小説の要素がほどよく混じり合っています。
2005年5月27日発行 第16号から抜粋(1件)
ナンシー・ファーマー・作/小竹 由加里・訳
『砂漠の王国とクローンの少年』(DHC)
初めて知る作者、なじみのない出版社、そしてこのタイトルでは、どこかの書評で見かけた記憶がなければ、見逃したまま読まなかった可能性が高いと思います。
事前に題名から予想したのは、クローンを刺激的に扱った、俗っぽい冒険譚でした。しかし、この作品には社会性と不気味なリアリティがありました。
全編はクローンの少年の視点で描かれています。クローンとして誕生したマットは、やがて自分が何者であるのかを知り、自分を取り巻く世界の現実の姿を、少しずつ認識していきます。描かれた近未来の社会は読者にとっても謎だらけで、そこで何が起きているのか、彼の身の上にこれから何が起きるのかを、マットとともに一つ一つ知らされていくことになります。
読めない展開、意外な結末、個性的で存在感のある登場人物たち……。
クローン人間を題材とした物語は、題材の今日性に寄りかかって、得てして発展性のない教訓話に陥ってしまう傾向があると感じています(曰く、クローンを作るのは倫理にもとることである、クローン人間はこの世にあるまじき悲しい存在である……云々)。
この作品からは、あらゆる人間が運命(遺伝子)ではなく自分の意志で生き方を選んでいくことへの、励ましのメッセージをも受け取ることができました。
映画化される予定もあるそうです。
ちなみに、クローン人間が登場する作品のうち、これまでの読書歴で一番好きだったのは、U・K・ル=グウィンの「九つのいのち」(短編集『風の十二方位』所収)でした。
2005年3月21日発行 第15号から抜粋(1件)
ジャッキー・フレンチ・作
さくま ゆみこ・訳
『ヒットラーのむすめ』(鈴木出版)
南半球の国、オーストラリアの作品です。……と、わざわざお断りするのは、ドイツに近い「オーストリア」と読み間違えないためです。登場するのは、スクールバスを待っている現代の子どもたち。あのヒットラーとは何の関わりもなさそうな舞台から、この物語は始まっています。
バスを待つ間の「お話ゲーム」という設定で、「ヒットラーのむすめ」の物語が、少女アンナによって語られていきます。
もしも、自分の親が悪いことをしたとしたら、そのときどうすればいいのか、それが間違っていると、どうすれば知ることができるのか。親が悪いことをしたとき、止められなかった子どもにも罪はあるのか……。
聞き手の一人である少年マークは、真剣に考え抜きます。
周囲の大人たちは、遠い昔の外国のヒットラーについては明快に答えますが、自国の先住民アボリジニーに話が及ぶと、急に不機嫌になります。
興味深い題材を扱った、新しい切り口の作品でした。具体的で読み易い文章で書かれているので、子どもたちもテーマの重さにつぶされることなく、どきどきしながら読み進めるでしょう。物語の最後には、衝撃的な種明かしがあります(大人の読者には予想がつくと思いますが)。
作者のジャッキー・フレンチは過去十年間に百冊を超える本を出版している(巻末の著者紹介による)そうですが、まだ日本で翻訳された作品を知りません。おそらく『ヒットラーのむすめ』が最初の紹介ではないかと思います。
2005年1月21日発行 第14号から抜粋(2件)
ダイアナ・ウィン・ジョーンズ・作
野口 絵美・訳/佐竹 美保・絵
『呪われた首環の物語』(徳間書店)
知らない作者の作品だったら(面白い作品を期待できる作者でなかったら)、このタイトルでは手に取らなかったでしょう。ホラーは苦手です。
でも、これは全くホラーではありませんでした。ケルトの伝説を取り入れたファンタジーであり、とても現代的な友好の物語でもあります。
この物語には同じ湿原で暮らす〈人間〉と〈巨人〉と〈ドリグ〉の三つの種族が登場します。タイトルになっているのは、〈ドリグ〉の少年が〈人間〉の少年に殺される直前に呪いをかけた首環のことです。この首環の呪いが、直接の敵である〈人間〉だけでなく、〈巨人〉にも災厄を及ぼしていきます。
読者は〈人間〉である主人公ゲイアたちに寄り添って読み進めるうちに、やがて作者がしくんだ仕掛けに気づくことになります。
とても吸引力のある作品でした。冒頭近くの、どんな色合いの物語なのかも分からない時点から、作者の語り口に引きつけられて、本を手放せなくなりました。
また、初めの方にいくつもの謎が仕組まれていて、いったいどう解き明かされていくのだろうという興味からも、目が離せません。
最後は、それぞれの種族の子どもたちへの期待と共感で満たされて、感動をもって読み終えることができました。
ダイアナ・ウィン・ジョーンズの作品は「ハウルと動く城」(原作『魔法使いハウルと火の悪魔』)の映画化のおかげでしょうか、近ごろ翻訳ラッシュのようです。『花の魔法、白のドラゴン』(徳間書店)、『デイルマーク王国史』四部作(東京創元社)ほか、昨年だけでも多数出版されています。
岡崎 ひでたか 作/小林 豊 画
『鬼が瀬物語 魔の海に炎たつ』(くもん出版)
漁師にとって危険に満ちた魔の海域。明治の初期、船大工の息子としてその漁村に育った満吉は、身近な人々の遭難に接し、漁船の改良を目指します。
物語は、少年時代の印象的なエピソードに始まり、満吉が志を貫いていく過程を追っています。素材は地味ですが、なかなかにドラマチックなところもありました。
船大工が釘を打つまでに手間をかけ、手抜きのない作業をするように、作家も当時の資料を調べ上げ、構想をふくらませて、読み応えのある作品に仕上げています。
 上に戻る 上に戻る

本紙は、A4表裏2面の情報紙(隔月刊)です。
|